保育所・認定こども園・幼稚園の利用について
保育所・認定こども園・幼稚園の利用手続について
保育所・認定こども園を利用するためには「保育給付認定(2号又は3号認定)」が必要です。
保育給付認定を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
- 保護者の居住地が藤崎町である
- 保護者が「保育を必要とする事由(就労など。以下「保育事由」という。)」に該当している
※幼稚園や認定こども園の教育利用(1号認定)を希望する方は、施設へお申込みください。
教育・保育給付認定の種類
| 認定区分 | 対象 | 給付の内容 | 利用できる施設 |
| 1号認定 |
満3歳以上の就学前子ども ※2号認定を除く |
教育標準時間 |
幼稚園 認定こども園 |
| 2号認定 |
満3歳以上で保護者の保育事由により、 保育を必要とする子ども |
保育標準時間 保育短時間 |
保育所 認定こども園 |
| 3号認定 |
満3歳未満で保護者の保育事由により、 保育を必要とする子ども |
保育標準時間 保育短時間 |
保育所 認定こども園 |
子ども・子育て支援新制度の詳細はこちら(こども家庭庁ホームページ)
町内施設一覧(令和8年4月1日予定)[PDF 440 KB]
※最新の状況は「ここdeサーチ」や施設への問い合わせによりご確認ください。
入所申込みの受付期間・受付場所
受付期間
入所を希望する月の前月5日(5日が閉庁日の場合、次の開庁日)まで
例:7月1日入所希望の場合は6月5日(6月5日が日曜日なら6月6日)
※4月1日入所希望の申込みは、1月の開庁日に受付します。
※転入による入所申込みは、転入手続きと同時に行ってください。
受付場所・受付時間
役場1階 住民課子育て支援係(④番窓口)
午前8時15分から午後5時まで(水曜日は午後6時30分まで)
申込みに必要な書類
詳細は入所申込みのご案内[PDF 340 KB]![]() をご確認ください。
をご確認ください。
子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書
※入所希望の児童ごとに1部提出してください。
※育児休業給付金の支給対象期間延長手続きには、申込書の写しが必要です。(必要な方は町に提出する前にコピーを取ってください。)
保育事由を証明する書類(父母ともに必要)
※申請後に保育事由が変更となった場合、変更後の書類を提出してください。
正当な理由なく提出しなかった場合、保育給付認定の取消し・利用施設の退所手続きを行うことがあります。
就労
(注)就労証明書に以下のいずれかがある場合のみ受付します。
- 事業所印の押印
- 代表者名もしくは担当者名の署名(手書き)
妊娠・出産前後(就労・障がいなど他に保育事由の無い場合)
- 母子健康手帳の写し(氏名と出産予定月記載ページ)
疾病・けが
※児童の保育が困難であることが記載されているもの
心身の障害(以下のいずれか)
- 障害者手帳の写し(氏名、等級、交付年月日記載ページ)
- 特別児童扶養手当又は障害基礎年金の受給を証明する書類の写し
同居親族の介護・看護(以下のいずれか)
- 介護保険被保険者証の写し(氏名、等級、交付年月日記載ページ)
災害復旧活動
- り災証明書などの写し
求職活動・起業準備
- 求職活動申立書:[Word 17 KB]
 /[PDF 92 KB]
/[PDF 92 KB]
- 継続的な求職活動を行っていることを示す書類があれば添付(ハローワーク受付票の写しなど)
就学・職業訓練校等における就業訓練
- 在学(籍)証明書又は受講決定通知等(氏名及び受講期間が記載されたもの)の写し
- 受講状況がわかるカリキュラム表などの写し
保育料算定に必要な書類
以下のいずれかに該当する場合、追加資料が必要となることがあります。
- 保護者の住所が前年又は本年の1月1日に町外であった
- 児童又はその同一生計の者が障害者手帳等の交付を受けている
- 保護者が別居している児童を監護している(県外の高校に通っている等)
詳細はこちら[PDF 340 KB]![]() (2ページ目)
(2ページ目)
入所の決定(利用調整)について
保育所等の利用申込みがあったとき、世帯の状況等を審査し、優先度を指数化して指数が高い児童から順に入所を決定(利用調整)します。
定員超過や保育士不足などにより、希望施設に入所できないことがあるためご留意ください。
保育料について
保育料は父母(注)の市町村民税所得割額合計額で算定されます。
4月から8月分までは前年度の市町村民税、9月から3月分までは当年度の市町村民税により算定されます。
保育料利用者負担額表(3号認定)[ 118 KB pdfファイル]![]()
保育料利用者負担額表(3号認定・ひとり親等)[ 121 KB pdfファイル]![]()
保育料は、児童の保育に要する費用の一部を保護者に負担していただくものです。期限内に納付してください。
(注)父母の所得合計が一定以下の場合、収入が最も大きい同居親族を家計の主宰者と認定し、算定に加えます。
幼児教育・保育の無償化
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化(こども家庭庁ホームページ)が始まりました。
その他
保育所・認定こども園について、よくある質問をまとめましたので参考にしてください。


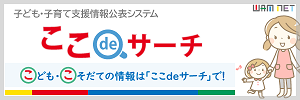


 前のページに戻る
前のページに戻る ホームに戻る
ホームに戻る 先頭に戻る
先頭に戻る